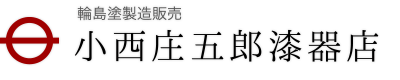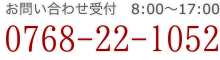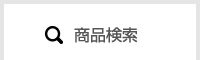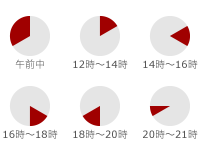現在、能登半島地震のため店舗業務を全停止しております。
ネット注文につきましても、配送再開の目途が未定のため
受付も全停止中しております。
お客様には多大なご迷惑をおかけ致しますがご容赦ください。
当店の漆器は、天然木に、天然漆で塗った丈夫な輪島塗です。
輪島塗の工程は、数十にも及び、日常使いの中での熱や衝撃に耐えるために、さまざまな工夫がなされています。
(下の表をご覧下さい)
とはいっても合成樹脂の製品と違い、食器洗浄機や電子レンジの高温、冷蔵庫の冷温への耐性はなく、輪島塗はこれらの家電製品に使用することはできません。その意味では、丈夫とはいえない、ちょっと使いづらい、と思う方も多いでしょう。
では、輪島塗を使うメリットはなんでしょうか?
1つは、天然木ならではの良さがあります。
断熱性と保温性です。お椀にアツアツのお味噌汁を入れても、その熱が手や唇に直接伝わりにくく、それでいて中身の温かさは長持ちするのです。
2つめは、天然漆を使った輪島独特の下地です。
天然木の器はそのまま使うより、何かしら塗料を塗ったほうが丈夫になります。そのために、人々は昔から、身近な天然塗料である漆を塗った器を使ってきました。
輪島では、漆を使って最大限に木のボディを強化するため、独特の下地法「布着せ本堅地」を行っています。
木の弱い部分や継ぎ目を補強する「布着せ」という作業。
輪島産の良質な珪藻土を使った下地方法、「本堅地」。
たくさんの手間をかけて、100%天然素材のぬくもりある器が完成します。
そして3つめは、修理ができることです。
ボディから上塗りまで、100%天然の材料で作るからこそ、傷んでもまた同じ材料を使って修理すれば、新品同様に生まれ変わります。
(→「修理」を参照)
1.木地 漆器によって木の種類は違い、椀や皿は主にケヤキを用いる。 |
2.切彫 木地の接合部、小節や割れ目など、木地の悪いところを小刀で削る。 |
3.刻苧 切彫したところへ、刻苧漆(ケヤキの粉と糊漆にを混ぜ合わせた下地)を詰めて平らにして傷を補修する。 |
4.木地固め 全体に生漆をしみこましせ、木地の吸収性を防止する。 |
5.木地磨き 次に塗る漆の接着をよくするために、サンドペーパーで木地を磨く。 |
6.布着せ 椀の縁や高台など薄く壊れやすい箇所に、糊漆で布(麻布や寒冷紗)を貼り補強する。輪島塗の重要な工程の一つです。 |
7.着せ物削り 布着せした布の縁や重なった箇所を削り滑らかにする。 |
8.惣身付け 木地と布着せの段差をなくすために、惣身漆をヘラを使って塗り、平らにする。 |
9.惣身磨き 荒砥石で全体を空研ぎする。 |
10.一辺地付 ※一辺地漆(一辺地漆・生漆と少量の米糊、一辺地の粉を混ぜたもの)を、一つの面ごとに何回かに分けてヘラで下地付けをする。 |
11.一辺地研ぎ 荒砥石で全体を空研ぎする。 |
12.二辺地付 二辺地漆(二辺地漆・生漆と少量の米糊、二辺地の粉を混ぜたもの)を、一つの面ごとに何回かに分けてヘラで下地付けをする。 |
13.二辺地研ぎ 荒砥石で全体を空研ぎする。 |
14.三辺地付 三辺地漆(三辺地漆・生漆と少量の米糊、三辺地の粉を混ぜたもの)を、一つの面ごとに何回かに分けてヘラで下地付けをする。 |
15.三辺地研ぎ 荒砥石で全体を空研ぎする。 |
16.めすり 下地のはだを細かくするために、目摺漆(生漆と水練りした砥粉をまぜたもの)をヘラで薄く付ける。 |
17.地研ぎ 十分乾燥したあと、砥石を使って全体を丁寧に水研ぎする。 |
18.中塗 全体に中塗漆を刷毛で塗る。中塗漆は下地層に染み込み下地をさらに堅く固める効果がある。 |
19.中塗研ぎ 青砥石、または駿河炭で塗面全体を平滑になるまで水研ぎする。 |
20.小中塗 再び刷毛で中塗漆を全面に塗る。 |
21.拭き上げ 青砥石、または駿河炭で塗面全体を平滑になるまで水研ぎする。その後、上塗を美しく仕上げるために油分や汚れを丁寧に拭き取る。 |
22.上塗 最上質の上塗漆を刷毛で塗る。上塗はゴミやほこりをきらい、適度、適湿の塗部屋で行われる。 |
23.呂色 上塗りの後、艶を出すために行う作業で、鏡のような光沢を与える。傷をつけないようにするために、最後は人の手や指で磨き上げる。 |
24.蒔絵 筆に漆をつけて絵を描き、金粉、銀粉などを蒔く。固まったあとで研いだり磨いたりして光らせる。 |
25.沈金 絵を、ノミを使って点や線で彫り、彫ったところに金や金箔を入れる。 |
※ 一辺地漆とは、輪島の山でとれる珪藻土を蒸し焼き、砕いてふるい分けた「地の粉」を糊漆に混ぜたもの。地の粉は堅くて丈夫な下地を作る原料となる。粒子の荒い順に一辺地の粉、二辺地の粉、三辺地の粉がある。 |
||